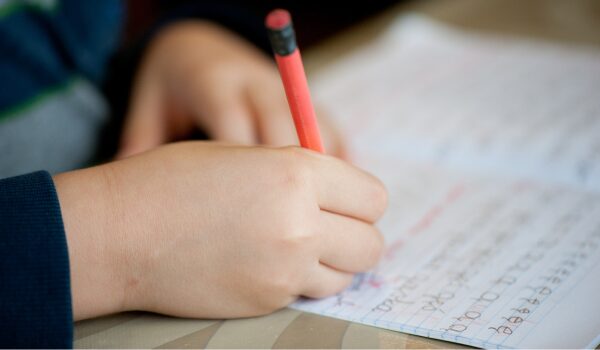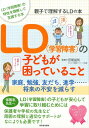学習障がい
お子さんに、こんな症状はありませんか?
- 字が読めない。読めはするけど綺麗とは言えない。
- 書くことをあまり好まない。
- 文字を思い出すまでに時間がかかる。
- カタカナ・漢字がなかなか覚えられない。
- 「ゃ・ゅ・ょ」の使い方がなかなか覚えられない。
- 「っ」を忘れたり、「ッ」がおかしな場所に入っている。
- 音読がぎこちない。
学習障害とは
学習障害とは、全般的に知的発達に遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態をいいます。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00808.html
 ゆん
ゆん私の息子の場合、ワーキングメモリが弱く文字の読み書きが苦手なことから、「聞く」「読む」「書く」に困難さを抱えていて、検査の結果、大体2学年の遅れがあります。
逆に「計算する」「推論する」は得意で、学年相当より少し上にいます。



頭ではわかっているのに表現しづらい状態で、もどかしさを感じているのでは…。
学習障害の原因
学習障害(LD)の原因は分かっていません。目や耳、皮膚などさまざまな感覚器官を通して入る情報を受容し、整理し、関係づけ、表すという脳機能になんらかの機能障害があると考えられています。
学習障害は生まれ育った家庭や環境、つまり、家庭でのしつけや育て方が原因ではありません。学習障害のある子どもの特性や支援は一人ひとり異なります。環境を整え、学習方法を工夫することで困難を軽減することができます。
https://life.litalico.jp/hattatsu/ld/
学習障害の診断方法
学習障害(LD)は小学校に入学して、本格的に学習をするようになってから判明することが多いといわれています。保育園や幼稚園のころは、文字を書いていても鏡文字になることも珍しくなく、計算や漢字も習うこともあまりないため、学習障害の傾向があっても気づく機会が少ないためです。
小学校に通うようになってから「似た文字をいつも間違えてしまう」「数は数えられても計算になるとできなくなる」などの特定の学習だけが苦手という場合は、発達障害の診断ができる病院を受診してみるといいでしょう。
発達障害の診断は予約や紹介状が必要なことがありますので、どの医療機関を受診していいか迷う場合は、かかりつけの小児科、発達障害者支援センター、自治体の障害福祉窓口などに相談してみましょう。
診断の流れは医療機関ごとに異なっていますが、多くはまず問診でどんな学習が苦手なのか、それまでの成育歴や既往症などが聞かれます。
その後、知能検査や発達検査といった心理検査がおこなわれます。場合によっては脳波の検査などで、脳の疾患について確認することもあります。検査は一日で終わるわけではなく、数日に渡って行われていきます。そして、すべての検査が終わってから問診や各種検査の結果をもとに診断が下されます。
医療機関で診断を受ける場合は、『DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版』に基づいて「限局性学習症/限局性学習障害」という診断名がつくことが多くなっています。
https://life.litalico.jp/hattatsu/ld/
↓ 以下も参考にしてみてください ↓
DCD(発達性協調運動障がい)
DCDとは
発達性協調運動症とは、運動が上手にできない「不器用」を呈する発達障がいのひとつです。英語では「Developmental Coordination Disorder(以下DCD)」と呼ばれています。
https://kousuke-3.com/dcdkomarigoto/
運動は粗大運動と微細運動に分かれています。
粗大運動は姿勢を保ったり身体全体を大きく動かすような運動です。
具体的には、走る・ジャンプするなどの運動を指します。
微細運動は手や指を使った細かい動作を必要とする運動です。
具体的には、字を書いたりハサミを使うなどの運動を指します。
DCDでは粗大運動が苦手な子・微細運動が苦手な子・粗大運動も微細運動も苦手な子がいます。
5歳から11歳のお子さんの5〜6%の割合でDCDを有していると言われており、幼稚園・学校のクラスに少なくとも1人はDCDを有するお子さんがいる可能性が高いことがわかります。
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、【LD・SLD(限局性学習障がい)】などの発達障がいとの合併率が高く、そちらの特性が目立つため、不器用さというDCDの特性は見過ごされがちです。
https://mywonder.jp/pripri_palette_post/34784/ ・【括弧内筆者】
心身の成長著しい幼少期や学童期の子どもが、不器用さによる劣等感などで苦しむことがないように、DCDに対する理解を深めることが大切です。



むすこも現在、一応診断として学習障がいとDCDと言われているけど、ADHDを合併していそう…
お子さんに、こんな症状はありませんか?
粗大運動では
・走り方がぎこちない
・物によくぶつかる
・縄跳びが飛べない
・階段の昇り降りがぎこちない
・自転車に乗ることができない微細運動では
・お箸を上手く使えないため食べこぼしが多い
・文字を書くと枠からはみ出してしまう
・ハサミを使って紙を上手に切れない
・靴ひもが結べない
・洋服のボタン、ファスナーを止められない以上のように、不器用さは運動だけではなく生活面でも影響を与えます。
https://kousuke-3.com/dcdkomarigoto/



むすこは比較的、粗大運動はできるけど微細運動の苦手さが目立つかな。
靴ひもやビニール袋を小さくするために結べないとか。
食べこぼしも多いし、文字もはみ出す。
でも粗大運動の、物によくぶつかるというのも当てはまる。



DCDと言っても、全て当てはまるわけではないのかもね。
DCDの原因
発達障害の原因は、先天的な脳の機能障害です。
それに加えて遺伝的な要因や環境要因など、さまざまなものが複合的に関係すると言われています。「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足が原因」などという説は現在では医学的に否定されています。
https://snabi.jp/article/9#8g6t8
劣等感を感じやすい
DCDを有するお子さんは自尊心・自己肯定感・レジリエンスといった自己に対する評価が低下しやすく、抑うつ障害や不安障害へ繋がりやすいことが指摘されています。
DCDは不器用を呈する運動の困難さが特徴ですが、遊びやスポーツに取り組む楽しさを低下させ子ども自身から運動をする意欲を失わせていきます。
その結果、体力低下や肥満を引き起こすといわれています。
また、運動における失敗体験の積み重ねは自尊心や自己肯定感、レジリエンスも低下していきます。
さらに集団で行うことの多いスポーツは、上手にできないという理由から仲間はずれにされてしまったり、最悪の場合イジメにつながってしまい不登校になってしたりするなど、子どもの心の成長に影響します。不器用さが子どもの心の成長に大きく影響を与えてしまい、心の問題に発展しさらに運動をしなくなってしまうという悪循環が指摘されています。
https://kousuke-3.com/dcdkomarigoto/



運動の苦手さは心の成長にも影響するから、早い段階で支援をする必要がありそうだね。



そうだね、早い時期に親が気付けるといいね。